| 1995 Winter | |
| 1995 Winter | |
無立木地や荒廃した産地が少なく、山岳、高原、渓谷美など自然の地形を備える九頭竜川。流域は四季折々の変化に富み、清らかな水の流れもあって数多くの植物や生き物の棲息地にもなっている。深い雪に閉ざされる冬、九頭竜川にどんな風景が見られるのか紹介しよう。 |
 九頭竜の冬といえば、真っ先に見られるのが毎年、11月初めごろから始まる「サケのそ上」だ。ここ数年、上流からの澄んだ水が放流されていることもあって、産卵を控えたサケがどんどん戻ってきている。九頭竜川の下流、天池橋付近に行くと、橋の上や土手などから活きのいいサケの姿をたくさん見ることができる。 九頭竜の冬といえば、真っ先に見られるのが毎年、11月初めごろから始まる「サケのそ上」だ。ここ数年、上流からの澄んだ水が放流されていることもあって、産卵を控えたサケがどんどん戻ってきている。九頭竜川の下流、天池橋付近に行くと、橋の上や土手などから活きのいいサケの姿をたくさん見ることができる。「一説には、和泉村にあるダムの一部を放流してから魚が戻ってきたといわれています。水がきれいになって地元の奥越漁業組合をはじめ、多くの人たちが喜んでいるんですよ。」 そう目を細めるのは、長年、九頭竜川の環境整備に取り組んできたドラゴンリバー交流会事務局長の木幡雅好さん。 北陸の河川の中でも、九頭竜川はとりわけ自然のままの姿をとどめているという。それだけに、冬が近づくとサケはもちろん、たとえばガン、マガモをはじめ、タンチョウヅルなどの渡り鳥も流域にたくさん飛来する。まさに生き物たちの楽園なのだ。そんな九頭竜を知る人たちにとって、きれいな水は生き物たちを呼び寄せる自然の恵みともいえよう。 |
冬の魚はサケばかりではない。九頭竜川に欠かせない特有の魚として「アラレガコ」がよく知られている。初冬の産卵期に、霰(あられ)にうたれながら川を下ることからその名がついた。地元では「カマキリ」「カクブツ」とも呼ばれその生息地域が「天然記念物」に指定されている。  1シーズンに数えるぐらいしか捕獲できないことから非常に希少価値が高く、昔から「高位高官しか口にできない」高級魚とされてきた。それだけに、本当の食通には、こたえられない冬の風物詩なのだ。 1シーズンに数えるぐらいしか捕獲できないことから非常に希少価値が高く、昔から「高位高官しか口にできない」高級魚とされてきた。それだけに、本当の食通には、こたえられない冬の風物詩なのだ。九頭竜川に詳しく、数多くの著書も執筆している上杉喜寿さんは、アラレガコについてこう力説する。 「地元では越前ガニと並ぶ冬の代表的な風物詩ですね。だけど、数が少ないからアラレガコの方がずっと貴重でしょう。体長は大きいもので30センチぐらい。頭が大きくて、背中は茶褐色。冷涼で本当にきれいな水の中でしか棲息しない魚です。ずいぶん前に一度だけいただいたことがあります。おいしかったですよ。今はもう”貴族”しか口にできない高級魚ですね」 九頭竜川は、貴重な魚を生かす天然の”いけす”でもあるのだ。 |
それにしても「限られた人しか獲らないし、料理していない」という貴重なアラレガコは、1シーズンで一体どのくらい獲れるものなのか。松岡町で川魚料理店「ゆう徳」を営む岩本徳穂さんに尋ねてみた。 「一回の漁でせいぜい2〜3匹程度です。平成6年は50〜60匹ぐらい獲れたんじゃないかな。機関は11月下旬からだいたい2月一杯。少ないと思うでしょうが、それでも最近は水がきれいになって増えてきたんです。なにしろ、成魚になるまでに7〜10年ぐらいかかるから乱獲はできない。一番獲れた時で4〜5年前に1シーズン300匹ぐらいという年がありました。何年ぶりかの豊漁で、皇室にも献上したんですよ」  アラレガコの捕獲法は、エバ網というこの地方独特の漁法で行われている。アラレガ降って荒れた寒い日を選んで網を張るそうだ。 アラレガコの捕獲法は、エバ網というこの地方独特の漁法で行われている。アラレガ降って荒れた寒い日を選んで網を張るそうだ。アラレガコの料理方法だが、貴重な魚だけに「捨てるところがない」とか。岩本さんによれば「甘露煮、唐揚げ、刺身、鍋、塩焼きといったところが一般的」 いずれにしても、水質の良いところにしか棲息しないアラレガコは、九頭竜川の美しさを物語る貴重な生き物であることは間違いない。それでも、聞くところによれば一時は絶滅の危機に瀬していたという。 しかし今、川にきれいな水が戻るにしたがって年々少しずつ増えてきている。九頭竜川の水は、ここでも大切な生き物を守っているのだ。 |
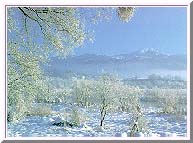 サケ、アラレガコ、エバ漁法、ガン、カモ、タンチョウヅルなど、冬の九頭竜川を彩る風物詩を見てきたが、美しい風景を代表するものにもうひとつ「樹氷」がある。 サケ、アラレガコ、エバ漁法、ガン、カモ、タンチョウヅルなど、冬の九頭竜川を彩る風物詩を見てきたが、美しい風景を代表するものにもうひとつ「樹氷」がある。これも最近ではめったに見られなくなった風物詩のひとつだ。それでも前出の上杉さんによれば「上流にあたる勝山市、大野市の山手に行くと、だいたい1〜2月の朝早くに柳の樹氷を見ることができる」そうだ。九頭竜の冬の美しさを体感するには是非一度足を運んでみたいところだろう。 上流といえば、毎年深い雪に覆われる。ここ数年、かつてのような豪雪は見られないもののそれでも山間部では1メートルを越える積雪は珍しく、ない。そんな地域で見られたものに「雪囲い」がある。九頭竜の昔を知る人には「かつては冬を物語る風景のひとつ」であったという。 ススキの穂が散ったあとの萱をたくさん切って束にし、それで家の回りを囲った雪囲いは、長年、雪に埋もれた中で生活してきた人たちの知恵から生まれたものだ。雪と闘い、その雪をどう克服するか。それもまた、九頭竜の厳しい冬を知る断面といえよう。 すばらしき自然の造形が、いまなお残る九頭竜川。生き物たちの楽園である流域にもうすぐ本格的な冬の寒さが訪れる。 |
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | ||||