| |
1997 Autumn |
|
|||
竹田川は、丸岡町内にある「丈競べ山」付近を源流とする延長41.9キロメートル、流域面積211平方キロメートルの河川。全体として福井県の北西方向に流下し、河口付近で九頭竜川に合流し日本海に注ぐ。 いまでこそ豊かな自然と水のきれいな川として知られているが、竹田川はむかしからよく氾濫する川だった。このため集落では、氾濫や洪水から集落を守るため、何度となく闘いの歴史を繰り返してきたようだ。  竹田公民館館長の江川俊和さんは、川と住民の暮らしについてこう説明する。 竹田公民館館長の江川俊和さんは、川と住民の暮らしについてこう説明する。「竹田川の集落は、四方を山に囲まれた平地の少ないところで、資料によればむかしから米作りにはあまり適していなかったようです。ただ水量豊富な竹田川が流れていましたから、この水を引いて用水をつくれば米がつくれるということで、歴史的には明治9年ごろ初めて山竹田用水が敷かれ、米作りが少しずつ行われるようになるんです。それまではアワ、ヒエ、ソバといった畑作ですね。用水がつくられて川の流れもいくぶん変わったのではないでしょうか。ただ、氾濫や洪水がほとんどなくなったのは龍ヶ鼻ダムができてからですけどね」 |
|||
ダムの建設で氾濫や洪水と闘ってきた歴史に終止符を打った竹田の集落から、今やすっかり”山間の里”の面影は薄れつつある。とはいえ集落の住民と、竹田川を含めた周辺の自然との共生は、むかしからちっとも変わらない。 竹田の集落内に「千古の家(坪川家)」という、およそ700年前に建てられた民家がある。昭和41年に国の重要文化財に指定され、44年に当初の形態に復元された。それまで、坪川家の持ち家として代々引き継がれてきた。その坪川家には、竹田という土地柄、環境を選んで住み着いた人間と、自然との「共生」の歴史がそのまま色濃く投影されている。 坪川家の先祖は、坪川但馬丞貞純。北面の武士で源三位頼政の後裔といわれている。宇治川の合戦で都を追われ、この地に定住した。周辺の集落を司る7人の名司の筆頭として高い格式をもち、近代になって丸岡町に統合されるまで代々村長を務める家柄であったという。 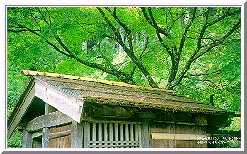 第30代当主にあたる松井ますみさんは、千古の家が700年近くも続いた理由についてこう振り返る。「この家がなぜここまで長持ちしたかというと、長持ちするための条件がひとつとして欠けていなかったからなんです。一言でいうなら、自然の摂理というものを理解して建てられているということでしょうか。たとえば、家のある場所は山々に囲まれた平地です。これは追手から逃れるための隠れ家には一番適していたし、米や野菜などの自給自足ができる場所も確保できる。目の前には山水が流れ、回りの木々や竹やぶは大雨や台風といった自然の災害から守ってくれる。日当たりが良く、適当に風通しも良いというように、もうここしかないというところを厳選して建てられています。家の中も釘は1本も使わず、通し梁で衝撃を吸収しやすいつくりですし。囲炉裏で火を燃やすと煤がでますが、これがまた木にはいいんですよ。松などの材料を使った家は、そんな条件の中でなら数百年は持つんですね。」 目を引くのはそればかりではない。たとえば台所だ。むかしは、山水を直接、家の中に引き込み流しにたまった水で洗い物や炊事をした。山の水は枯れることなく、いつも澄んでいたという。千古の家には、当時の流し台や農機具などがそのまま残されている。 「私がまだこの家に住んでいたころは、田んぼのあぜ道に茶の葉を植え、新茶を煎って山水を沸かして飲んだものです。それから囲炉裏で焚いた薪が炭になったら茶わんを洗い、それが終われば畑に戻して肥料にしました。その肥料が作物を育て私たちの口に入るわけです。自然の摂理を理解するということは、ある意味でそういう循環の大切さを知ることにもなるんじゃないでしょうか」 |
|||
 自然の摂理を理解し、人間自らが自然の一部となって生活する。それは、竹田という集落を厳選して定住した人間が、生きていくために必要になった術だった。その考え方は、坪川家に限らずある意味で、むかしから竹田という集落に住みついてきた人たちすべてに受け継がれている思想なのかもしれない。 自然の摂理を理解し、人間自らが自然の一部となって生活する。それは、竹田という集落を厳選して定住した人間が、生きていくために必要になった術だった。その考え方は、坪川家に限らずある意味で、むかしから竹田という集落に住みついてきた人たちすべてに受け継がれている思想なのかもしれない。竹田に住む辻端彦一さん(80歳)は言う。「ここに、芋洗いの道具がある。この中に里いもを放り込んで、川の中に沈めておくと水の流れが芋を洗ってくれてきれいに皮がむけるんじゃ。むかしはようけこんな道具があった。芋洗いは、竹田じゃまだ何軒も使うとるとこはあると思うよ。自然と暮らしてきた人間は、やっぱり智恵が働くもんなんじゃ。」 自然と人が共生するまち、竹田。川の清流、四季折々に姿を変える山里の風景とともに生きてきた人たちの智恵は、いまもなお集落の伝統としてしっかりと語り継がれている。 |
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | ||||